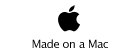郷土芸能

天照御祖神社例大祭、郷土芸能団体について -3-
2014年1月18日土曜日
天照御祖神社例大祭、郷土芸能団体について
2012、2013年度参加して
明治学院大学 DfSメンバー
(社会学科2年安部・政治学科3年永井)
3.鹿子踊り
荘厳で神聖、それでいて荒々しくダイナミック。鹿子踊りを一言で説明しようとすると、こんな言葉が頭に浮かびます。夜、満月の下で激しくも美しく舞う鹿子たちを初めて見たときの感動は、一生忘れることは出来ません。
吉里吉里の鹿子踊りは、南部藩最大の海産商である前川善兵衛によって約三八〇年前に伝えられました。それが広まり、現在大槌には鹿子踊りが四団体存在しています。海の町である吉里吉里の鹿子踊りには波を表現した荒々しさが含まれており、胴取り(鹿子の周りで笛や太鼓を演奏する人のこと)を担当していた方は「吉里吉里の鹿子特有の激しさは、これから先も絶対に失ってほしくないね。」と仰っていました。鹿子踊りには数多くの歌と演目があるのですが、一番の盛り上がりを見せるのは「つのかき」という演目です。二頭の雄鹿子が一頭の雌鹿子をめぐって戦い、胴取りの掛け声に合わせその争いは勢いを増していきます。頭を振り乱して争う二頭の鹿子は、思わず息を呑んでしまうほどの迫力でした。また、鹿子は新築の家や事故で亡くなられた方の家などを一軒一軒回っていき、仏様を慰める「霊呼」という歌をうたいます。住宅が並ぶ閑静な場所で笛の音が鳴り、太鼓の音が鳴り、歌が歌われ、鹿子たちが踊り始めます。祭りの賑やかな空間とはまた違う迫力がありました。
回る家の件数はその時々で変わるが、すべて終了するのは午後七時すぎです。それまでの練習の日々も合わせ、長くハードな時間をこなして行くのは本当に好きでないと困難だと思い、参加している子どもたちに「鹿子踊り好き?」と尋ねてみました。すると、「当たり前じゃん。大好きだよ。」「好きだから続けてるんだよ。」という言葉が返ってきて、何気ない言い方でしたが鹿子踊りが好きな素直な気持ちが伝わってきました。
鹿子踊りがこれからもずっと伝承されてほしいと心から思います。今でも耳を澄ませば笛の音が聞こえてきます。
(左上・右上写真)胴取りの方々
(右下写真)雌鹿子
(左下写真)雄鹿子